2028年秋をめどに、多くの民放AMラジオ局が放送を終了する方向で動いているのをご存じでしょうか?
「AMラジオ廃止はいつから?」という疑問を抱える方も増えてきた今、実際にそのスケジュールや背景を知ることはとても重要です。
かつて日常の一部だったAMラジオ。ファンとしては、その終わりに寂しさを感じずにはいられません。しかし一方で、FM転換やネットラジオなど、新たな可能性も広がっています。この記事では、AMラジオ廃止の具体的な時期、理由、そして私たちリスナーがこれからどう対応すべきかを、解説していきます。
この記事でわかること:
-
AMラジオ廃止のスケジュールと政府の方針
-
なぜ今、AM放送の終了が進められているのか
-
利用者にとっての影響と具体的な備え方
-
ワイドFMやインターネットラジオへの対応策
AMラジオ廃止はいつから始まるのか?政府方針と実証実験の概要

AMラジオが私たちの生活から静かに姿を消しつつある――そんな現実が、今少しずつ進行しています。かつては家の中や車の中で、深夜の音楽番組やニュース番組を楽しむ「日常の一部」だったAMラジオ。その廃止が具体的なスケジュールとして動き出している今、ファンとしては複雑な気持ちを抱かずにはいられません。
本記事のこのパートでは、AMラジオ廃止の具体的なスタート時期について、政府(総務省)の発表や、既に進められている実証実験の内容を中心に紹介します。「いつからどうやって廃止されるのか?」という疑問に対し、最新の制度・政策を丁寧にかみ砕いてお届けします。寂しさも感じながら、私たちはこの変化をどう受け止めるべきなのか。まずは事実をしっかり把握しましょう。
総務省による特例措置とは?
総務省が示した「AM局の運用休止に係る特例措置」は、2028年を目安にAMラジオ放送を段階的に廃止・休止していくための制度的な枠組みです。この特例措置では、まずは一部のAMラジオ局に対して試験的に放送を休止することを認め、将来的な本格廃止に備えて準備を進めることが目的とされています。
この措置が発表された背景には、AMラジオの送信設備が老朽化し、維持費が年々増加しているという現実があります。加えて、若年層を中心にAMラジオの利用率が低下しており、費用対効果の観点からも見直しが急務となっていました。
とはいえ、これまでAMラジオを愛聴してきたファンにとっては、「特例措置」と聞くだけでどこか物寂しい気持ちになるものです。制度としては現実的でも、文化としてのAMラジオが静かに終わっていくのは、やはり一つの時代の終わりを感じさせます。
第一期・第二期のスケジュールと対象局一覧
特例措置には「第1期」と「第2期」があり、2024年から2028年までの期間でAMラジオの放送休止が段階的に進められます。
-
第1期(2024年度):13社34中継局が対象。2月から順次放送を休止。
-
第2期(2025年度):追加で複数のAM局が対象予定。今後の実証結果に応じて決定。
これらの局は、単に放送を止めるわけではなく、FM放送(ワイドFM)やインターネットラジオなど、他の媒体での継続を模索しています。しかし、すべてのエリアでFM補完放送が十分に行き渡るわけではなく、聴取環境の格差が課題として残るのも事実です。
また、リスナーとしては、突然放送が終わるわけではないとはいえ、「いつから自分の好きな番組が聴けなくなるのか?」という不安を抱える方も多いでしょう。愛着のあるラジオ番組がひっそりと終わってしまうかもしれない――そんな現実が、段階的に近づいているのです。
AMラジオ廃止までの段階的スケジュール
AMラジオ廃止の全体スケジュールは以下のように整理されています:
-
2024年~2025年:一部地域で放送休止の実証実験(第1期・第2期)
-
2026年~2027年:実証結果を踏まえた制度整備・エリア補完の強化
-
2028年秋以降:原則として民間AM局の放送休止(ただし例外的な継続局もあり)
このように「いきなり終了する」のではなく、段階的に社会への影響を検証しながら慎重に進められている点は、リスナーにとっても少し安心できる材料です。
ただし、送信エリア外に住んでいる方や、ワイドFM対応機器を持っていない高齢者にとっては、情報の遮断というリスクが現実のものとなる可能性もあります。
AMラジオが担ってきた「緊急災害時の情報源」としての役割を、新たな媒体が完全に代替できるのか――この問いへの答えは、まだ完全には見えていません。だからこそ、私たちファンは「ただの放送の切り替え」としてではなく、文化と社会インフラの転換としてこの動きを見ていく必要があります。
AMラジオ廃止はいつから本格化?背景にある理由とFM転換の流れ
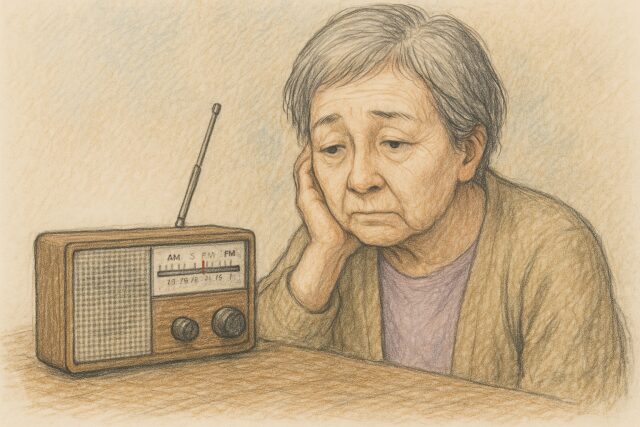
AMラジオが本格的に廃止される流れは、単なる時代の変化だけでは説明できない複雑な背景があります。ファンとしては「なぜ今?」と首をかしげたくなるかもしれませんが、実は技術的・経済的・社会的な複数の要因が絡み合っています。
ここでは、AMラジオ廃止の本格化がどのようにして進められてきたのか、その裏側にある事情を詳しく掘り下げていきます。老朽化したインフラの問題や、FMやネットへのリスナー移行など、知れば納得の面もありつつ、どこか切なさも拭えない――そんな「現実と感情」が交差する内容です。FM転換という新しい未来への動きの中で、私たちが何を大切にしていくべきか、考えるきっかけになるでしょう。
AMラジオの運営コストと設備老朽化の問題
AMラジオ放送は、実は非常にコストがかかるメディアです。大規模な送信アンテナや専用の敷地、そして老朽化した機器の維持・管理は、年々難しくなっています。多くの放送局が赤字経営を強いられており、特に地方局では設備更新すら難しい状況に直面しているのが実情です。
加えて、AM送信に必要な広大な土地も問題の一つです。都市化の進行で送信所周辺の地価が上がる中、採算が取れない中波放送に広い土地を確保し続けるのは、経営的に大きな負担です。
このような厳しい運営状況の中で、FMやインターネットといった低コストで柔軟な代替手段が存在することは、AM放送を続ける理由を徐々に薄れさせていきました。AMラジオの廃止が現実味を帯びてきたのは、こうした「技術的・経済的な限界」が背景にあるのです。
FM転換はなぜ必要?ラジオ放送の未来を探る
AM放送の終了とともに、注目されているのがFM放送への転換(ワイドFMを含む)です。FMは音質が良く、都市部でも受信しやすいというメリットがあります。また、既存のFMラジオ端末で聴けるため、AMに代わる手段として現実的です。
さらに、最近ではインターネットラジオやスマートフォンアプリも普及しており、放送の多様化が進んでいます。ラジオの役割は「音声メディア」として広がりを見せており、PodcastやYouTubeなどと並ぶ選択肢となりつつあります。
とはいえ、FMに転換してもすべての放送内容が引き継がれるわけではなく、AM特有の文化や放送スタイルが失われる可能性もあります。ファンにとっては、音質や利便性だけでは埋められない「味わい」があるだけに、完全な代替にはならないという思いもあるでしょう。
聴取環境の変化とスマホ・インターネット対応の影響
現代のメディア環境は、スマートフォンの普及とともに大きく変わりました。ラジオを聴く手段も、いまや専用機器に頼らずスマホで完結する時代です。radiko(ラジコ)などのアプリを使えば、全国の放送をタイムフリーで聴ける便利さもあり、AMにこだわる理由が薄れてきたとも言えます。
若い世代の多くは、ラジオを「放送」として受け取っていないケースも多く、むしろ音楽やトークコンテンツの「音声配信」として楽しんでいます。こうしたライフスタイルの変化が、AMラジオの役割を終わらせる方向に自然と進んでいったともいえるでしょう。
しかし一方で、スマホを持たない高齢者や、デジタル端末が苦手な方にとっては、こうした変化が「不便」や「孤立」につながる恐れもあります。ラジオは誰にでも開かれたメディアであってほしい――そんな想いが、AMラジオ廃止の議論のなかで静かに息づいているのです。
AMラジオ廃止はいつから現実に?利用者への影響と対策
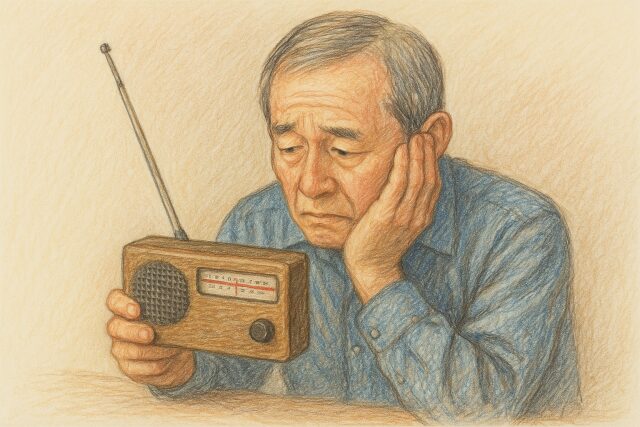
「AMラジオ廃止はいつから?」という疑問が、ついに現実的な問題として私たちの生活に影響を及ぼし始めています。すでに一部地域では放送休止が始まり、2028年には原則として多くの民放AM局が放送を終了する予定です。
ラジオを毎日のように聴いていた方にとって、この流れは「時代の変化」と受け入れるにはあまりにも急で、寂しさや不安を伴うものです。特に高齢者や地域によっては、ラジオが重要な情報源となっていることもあり、単なるメディアの切り替えでは済まない問題があります。
ここでは、実際にAMラジオ廃止が利用者にどのような影響を及ぼすのか、そしてその対策としてどんな準備ができるのかを紹介します。ラジオがこれからも身近で頼れる存在であり続けるために、私たち一人ひとりができることを考えていきましょう。
高齢者や情報弱者への配慮は?
AMラジオの最大の特徴は、「誰でも簡単に使える」という点にあります。スイッチ一つで情報が得られる手軽さは、特に高齢者にとって非常に重要です。しかし、FM転換やネットラジオへの移行が進む中で、「新しい操作が難しい」「スマホを持っていない」という声も多く聞かれます。
情報を得る手段が限られることで、情報弱者(デジタルデバイド)が生まれる懸念もあります。実際、総務省もこの点については認識しており、特例措置の中で「情報提供手段の確保」が重要視されています。
ただし、現時点では自治体レベルでの具体的な支援策が十分に整っているとは言えず、今後の対応が求められます。ラジオというインフラが、単なる娯楽ではなく「命を守る道具」であることを忘れてはなりません。
災害時のラジオの重要性と代替手段
災害時、テレビやインターネットが使えない状況下で、ラジオは命を守る情報源として非常に重要な役割を果たしてきました。特にAMラジオは広域に電波が届くため、非常時の連絡手段としても重宝されてきたのです。
しかし、AMの廃止によって「災害時にFMが同じ機能を果たせるのか?」という疑問も浮かび上がります。FMは都市部では受信しやすい一方で、山間部や海辺などでは受信しにくい場合もあります。
そのため、国や自治体ではワイドFMの普及や、防災ラジオの配布などを進めています。とはいえ、すべての世帯にそれが届くには時間がかかるのが現実。災害が多い日本において、情報伝達の手段が変わることのリスクは、慎重に見極める必要があります。
ワイドFM対応ラジオの準備・選び方
AM廃止に備えて、ワイドFM対応ラジオの導入は今からできる最も有効な対策の一つです。多くの家電量販店や通販サイトでは、「AM終了後も聴けるラジオ」としてワイドFM対応機器が販売されています。
選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう:
-
ワイドFM(90.0~95.0MHz)に対応しているか
-
災害時にも使える乾電池・手回し充電機能付きか
-
高齢者でも使いやすいシンプルな操作性か
特に高齢の家族がいる家庭では、早めにこうした機器を用意しておくことが大切です。また、自治体によっては助成金や配布事業を行っているケースもあるので、一度確認してみると良いでしょう。
ファンとしては、できるだけ長くAMラジオを聴き続けたいと思うのが本音かもしれません。しかし、現実的な対策を講じておくことで、「聴けなくなってしまった…」という事態を避けることができます。
AMラジオ廃止はいつから?まとめとして知っておくべきポイント
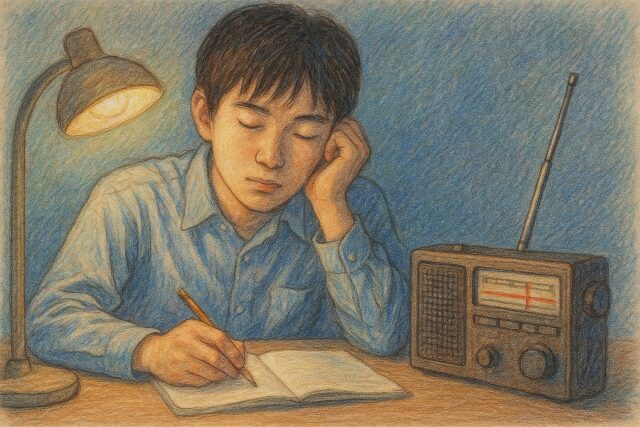
AM放送終了とFM転換の全体像
AMラジオ廃止の流れは、2024年の実証実験開始から2028年秋の原則終了に向けて着実に進んでいます。その背景には、運営コストの増大や設備の老朽化、そしてリスナーの聴取環境の変化があることがわかりました。
これまで生活の一部だったAM放送が終了するのは非常に寂しいことですが、FMやワイドFMへの転換によって、引き続きラジオを楽しむ方法も整いつつあります。
放送終了後のラジオの楽しみ方
AMラジオが終わったとしても、ラジオそのものがなくなるわけではありません。FM転換に加えて、radikoなどのインターネットラジオ、Podcastといった新しい形でも音声メディアは進化を続けています。
大切なのは「ラジオで何を聴くか」「どんな情報を得たいか」という点。使い方が変わっても、ラジオという文化が持つ温もりは、きっと次の形でも感じられるはずです。
情報収集やラジオ利用のこれから
今後は、ラジオを単なる娯楽から「暮らしに役立つ情報源」としてどう活用していくかが鍵になります。特に災害時や緊急時には、FM放送や防災ラジオの活用が重要です。
また、高齢者や情報弱者に向けたサポート体制の強化も課題です。行政の動きに注目しつつ、家庭でもワイドFM対応ラジオの準備を進めておくと安心です。
最後に、この記事のポイントをまとめます。
-
AMラジオは2028年秋に原則廃止される方向で進んでいる
-
廃止は段階的に進行し、2024年から実証実験が始まっている
-
総務省の特例措置により、複数局が放送休止を段階的に実施中
-
AMラジオの設備老朽化と運営コストの高さが大きな要因
-
FMやワイドFM、インターネットラジオへの転換が進んでいる
-
高齢者や情報弱者への対応が今後の大きな課題
-
災害時の情報源としての機能をどう代替するかが焦点
-
ワイドFM対応ラジオの導入が最も現実的な対策
-
放送終了後もradikoなどでラジオは引き続き楽しめる
-
ファンにとっては寂しいが、新しい形のラジオ文化が始まっている
AMラジオは多くの人にとって、単なる情報源ではなく「生活の音」として親しまれてきました。その終わりが見え始めた今こそ、私たちはその価値を見直すときなのかもしれません。
廃止の流れをただ受け入れるだけでなく、新たな形でラジオを楽しみ、未来に伝えていくことができる――そんな希望を胸に、次のステージへ進みましょう。



コメント